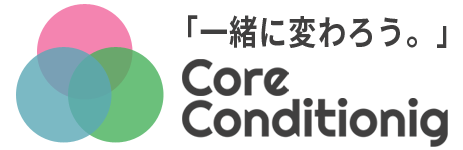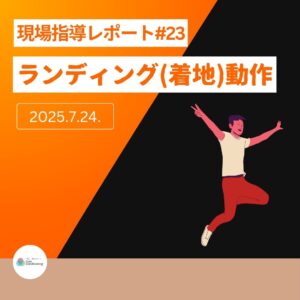NSCAジャパンが定期的に投稿している「NSCA PARK」最新の投稿は「速さと機敏さが勝敗を分ける?バレーボールのアジリティとトレーニング戦略」。バレーボールのコンディショニングについてまとめてありますのでご紹介しておきます。
この中で記されていたのが “横方向への動作が多い一方、大多数のストレングスエクササイズは矢状面(前後方向の動き)で行なわれる” 。
今回のテーマは「横方向への移動の強化」です。
<内容>
・横方向の強化
・3方向で鍛える
・ウォームアップドリルへの活用
●横方向の強化 チームは「ランディング動作」導入後、徐々に着地→横方向のドリルにターゲットを移行しています。理由は至ってシンプル・・横へ動くトレーニングをしないと、横へ移動する能力は改善されないからです。例えば、反復横跳びのような動きは”速く動く”ことは可能ですが、プレー中に求められる移動スピードは「停止から移動」または「ジャンプ着地から移動」がほとんどです。
また、理想の動きを完成させるには、股関節の外転可動域(脚を外へ開く動き)を立位で行うことが必要でした。また床を踏み込むには臀筋が必要です。
ドリルはラテラルホップ(横にホップしながら進むエクササイズ)をベースに、シャッフルやサイドステップを組み込むところから始めました。横方向に素早く、低く移動するためには片脚での筋力も必要なので、片脚スクワットを正しく行うことも同時進行で導入しています。
●3方向で鍛える 人間の動作は前額面(左右の動き)・矢状面(前後の動き)・水平面(回旋の動き)の3面上それぞれで構成されていますから、動作は3方向で考えます。横方向の動きは前額面上で行いますが、選手によっては股関節の外転筋力が弱く、スピードを上げると真横の姿勢で移動できず回旋の動きが入る場合も見受けられます。つまり、回旋動作を逆に”制御する(止める)”要因も必要な場合があります。これは体幹筋が関与してくるので腰椎骨盤リズムを観察しながら、弱点を指摘する必要がありました。
そもそも、水平面の動き(回旋)と矢状面の動き(前後)の区別がついていない選手がほとんどなので、これまでの指導を振り返っても、配慮が足りなかったと感じています。
●ウォームアップドリルへの活用 これらの横方向のトレーニングプログラムは、試合前の全体のウォームアップでも実施しています。つまり、試合ごとにアップの動きをチェックして、全体的な理解度と完成度を把握し、日頃のトレーニングで再指導またはレベルアップを図る、というPDCAサイクルで行なっています。
ここまでこだわっている理由は、今季は1試合目の設定が多いことが挙げられます。いかにスタートから「良い動き」を繰り返し引き出せるかと考えた時、選手自身が「良い動き」を認識しておく事と日頃から体に「良い動き」を叩き込んでおくことで、再現性の高いウォームアップを目指せるのではと考えています。
・スクワットジャンプやCMJ(カウンタームーブメントジャンプ)、アンクルホップからの停止→シャッフル
・ラテラルホップ→ブロックジャンプ
・変形スタート(ターン、クロスオーバー、バック走)→ダッシュ
・ツイスティング→クロスカントリー
この辺を今は主に取り入れていると思います。現在のドリルは秋季ファイナルリーグでの完成を目指していて、最終的なウォームアップドリルの完成形は、チームの集大成である全日本インカレで実施することを想定しています。
●まとめ エビデンスを基盤としたトレーニング指導は必須ですが絶対ではないなと思います。大事なのはそこを参考にしながらも、チームの選手の現状把握と段階的な導入だと思います。今回のブログも、単に私が今、横の動きにハマっているだけの事です・・
今回紹介したNSCAのコラムはバレーボールのコンディショニングについて素晴らしくまとめてあるので、是非参考にしてみてください。
参考文献:速さと機敏さが勝敗を分ける?バレーボールのアジリティとトレーニング戦略,NSCAジャパン,NSCA PARKより