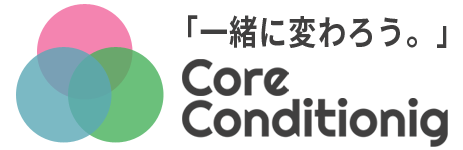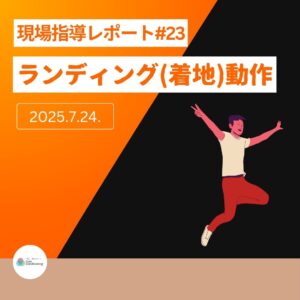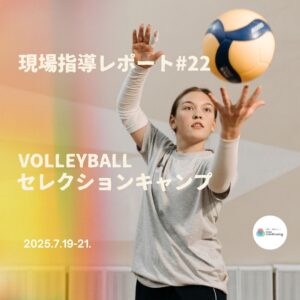世界バレー、凄かったですね。あのイメージで学生のプレーをみるとフィジカルの課題も多く見えてきすぎて、指導の励みになりました・・
今週末から秋季のリーグ戦も始まります!先週の国スポ予選の反省から改めてトレーニング内容をステップアップさせていきたいところですが、、基礎基本をもう一度指導し直しているところです
今回は「腰椎ー骨盤リズム」という、身体を扱う専門職の方にはお馴染みの身体機能を表現する言葉を取り上げて、バレーボールのパフォーマンスとどのよう関係があるのか、記録したいと思います
<内容>
・「腰椎ー骨盤リズム」とは
・プレーで観察される「腰椎ー骨盤リズム」の影響
・骨盤を安定させる
●「腰椎ー骨盤リズム」とは 骨盤が前や後へ傾くことで腰の骨(腰椎)が連動して上半身、下半身の運動に反映されることです。例えば腹筋が弱いと、骨盤が前に傾き「腰を反った」ような姿勢になり背中の筋が短縮した状態が続くことで痛みが発生したり、逆に背部の筋が弱いと腰が落ちて背中が丸くなり「猫背」になりがちです。このような可動性があるからこそ、いろんなプレーへの対応が可能になるともいえますが、何らかのバランスが崩れると障害の発生に繋がります。
バレーボール競技は腰痛の発症件数が多いので原因究明の視点で「腰椎ー骨盤リズム」には着目します。
技術指導においても、腰部の不安定性は選手のプレーの「なんで出来ないんだろう?」は少なからず関連する要因だと思います。
●プレーで観察される「腰椎ー骨盤リズム」の影響 体幹筋はプレー全般に関与しますが、バレーボールにおいて特徴的な姿勢である”構えの姿勢”への影響が最も懸念されると感じています。
”構えの姿勢”は股関節、膝関節、足関節を曲げた状態の”パワーポジション”と呼ばれる姿勢で、さまざまなスポーツにおける基本の準備姿勢でもあります。
この三関節がうまく使えることはジャンプ動作、アジリティ動作等を左右する重要なポイントなのですが「腰椎ー骨盤リズム」が正しく機能することは大事な要因になると考えています。
骨盤から腰の骨は5個、上には胸椎という胸の骨が12個連なっており、その先には頸椎7個、そして頭蓋骨と続きます。
それらを支える土台となる骨盤そして腰椎は上位に連続する背骨を介して肩・腕・手首に、最終的に「ボール」へと伝わる力に影響します。
バレーボールのオフェンスはそのほとんどが手を頭上に挙げてプレーを行いますが腕を振り上げた勢いに”負けて”腰が反ってしまう選手がいます。1つの理由としてジャンプの踏み込みの時点で骨盤が前に傾きすぎた状態でジャンプすると、前に跳んでしまう。結果的にボールを捉える位置が常に頭の後ろになり煽るようなスパイクフォームになる事があります。
本来ならば踏み込みの時点で回旋動作が誘導されると、回旋の作用を利用した空中姿勢が準備できるのですが、そもそも土台となるべき部位が崩れてしまうと、動作は崩れた先で行われ「プレーが安定しない」ことは想像できると思います。
人間の体はこのように骨が組み合わさって関節で動き、関節を動かす筋肉が力を発揮するのですが、一番大事な頭部が重力下で安定する構造になっています。現場でも「顎が上がっている(レシーブやスパイク、ブロックの時)」という指摘をよく耳にします。「顎を引く」ことでプレーが修正されるというより、身体のアライメント(骨格)の結果「顎が上がる」という見方をしています。
●骨盤を安定させる 骨盤を安定させる主な筋群は外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋のような深部筋と言われています。内臓に最も近い位置に存在する腹横筋が、バチっとコルセットのように機能してくれると、骨盤が直立し、股関節周りの筋も作用して・・立位になると今度は脚と体幹をつなぐ筋群(腸腰筋など)も関与します。言葉ではなかなか表現が難しいですが、先ほどのジャンプ動作も、骨盤を起こすお尻や裏ももの筋肉が強ければ、前に跳ぶ力を制御する事ができます。
横の動きや片脚で支えたり、体幹を回旋する際に機能する体側の筋も重要で、側屈動作のトレーニング(サイドベンドやサイドプランクなど)も導入しています。私はアウフバブトレーニング(下肢や上肢の動きを入れながら体幹を安定させる)を継続的に入れています。ちょっと使い方に工夫がいるので、繰り返しの指導が必要ですが、高校生こそやらせればできるようになります。
使うべき筋肉に刺激を入れると”構えの姿勢”が安定し、そこからのジャンプ動作、横へのステップの感覚が変わり、しっかり動けることでさらにさまざまな筋肉に刺激が入り、パフォーマンスにも大きく影響することが確認できます。選手も変化することはわかっていますが「使い方も含め、トレーニング」なので日々の練習の中で自分で動作コントロールができる(理解する)までには時間も必要です。選手の体の変化に対応しながら指導を続けることがトレーナーの仕事なので、そこは腹を括って向き合うしかないようです。
●まとめ 多くのバレーボール選手は、構えの姿勢一つとっても人それぞれ、オリジナリティに溢れています。これまではそれで良かったのかもしれない。けれど今以上の技術力を高めたければ少し身体を変える工夫が必要になる事もあります。荷重下で崩れてしまうような土台の上には安定した建物を築くことはできないのと同じで、結果的に意図しない「ケガ」に見舞われてしまうことや、頭打ちになる選手に多く出会ってきましたがこういう機会こそが、選手として大きく変わる一つのチャンスになるのも確かです。
もしかしたら「腰椎と骨盤」がうまく連動が取れていない事が、結果プレーを妨げたり腰痛やその他のケガの原因になってる事もあるかもしれません。体幹の強化は確かに大事ですが「なんのために、どのように強化するか」そして結果としての変化を誰の目から見てもわかるように、考えていきたいと思っています。