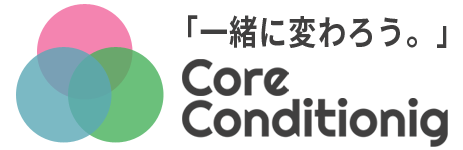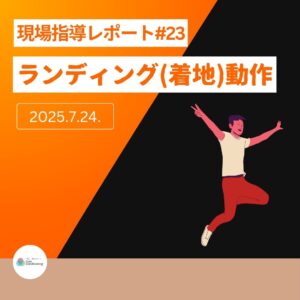高校生のチーム指導へ行きました。1年生のトレーニング指導を行ないました・・・といってもまずはフォームをやってみる、動きを覚える・・というところからのスタート。今回はフロアでできる自重エクササイズとウエイトフォームの指導をしました。
高校1年生は一番ケガをしやすい時期なのでできれば基本的な動きづくりを徹底したいところです。今回は高校1年生のトレーニングの目的と気づきについて記録します
<内容>
・体づくりの理解
・選手の特性を知る
・ウエイトトレーニング指導
●体づくりの理解
小学生からバレーボールをやってきている選手がほとんどですが、これまでの経験上、高校入学時までにストレッチングや動きづくりをやってきた選手はいません。高校生になり、バレーボールの練習以外でなぜこのような取り組みが必要なのかをこれから少しづつ時間をかけて教えていくのもトレーナーとして大事な役割です。最終的に、チームスポーツのトレーニングも個々それぞれで異なります。自分自身の体の特徴を知り、体をイメージ通りに動かしていくのは私ではなく、選手なので「なぜ体力トレーニングするのか」の意味はどの現場においても毎回伝えていく必要性があります。
選手の気持ちからすると「バレーボールと体力トレーニングのつながり」が伝わらなければモチベーションが上がりません。一番わかりやすいのは「スパイクとジャンプトレーニング」「レシーブとアジリティトレーニング」かもしれませんが、ジャンプトレーニングが本当にジャンプ力の向上につながるためには、スクワット動作やデッドリフトの動作、そしてつま先と膝の方向が同じになるような使い方でなければならないことを教え「だから、スクワットが正しくできることが大事なんだ」と理解に繋げていかなければならないと思っています(とにかく少しづつ、根気強く)。
●選手の特性を知る
前回のコラム「姿勢と動作」の中でも触れたように、姿勢はパフォーマンスに大きく影響します。逆に不良姿勢の原因がわかれば、それを直すエクササイズを行ない改善を図る。1年生の今の段階ではそこが一番の目的となります。今回提供したエクササイズは以下の通りです
・スクワット
・プッシュアップ
・エアプレイン
・フロントランジ
・サイドランジ
・四股踏み
・四股スクワット
「スクワットをしましょう、頭の後ろで手を組んで膝がつま先と同じ方向へ曲がるようにしゃがみ込みます」
このように伝えたとしても十人十色です。見せることである程度修正しますが、選手自身が”見る場所”によっては全くこちらの意図が伝わらない場合も多いのが、トレーニング経験のない選手の行動です。
ドリルのフォームは繰り返し時間をかけて教えていく覚悟が必要ですが、まず大事なのは選手一人一人の体や性格の特徴をこちら(トレーナー)が把握していくこと。このデータの積み重ねで指導の言葉掛けやレベルを把握をしていくことがこの先の指導に役立ちます。
新しい動作はできないことが多いのですが「片脚でバランスを取る(四股踏み、エアプレイン)」ドリルをわからずなりとも一生懸命やっていくと、さっきできなかったサイドランジがスッとできたり、スクワットが楽に感じたり・・・使うべき筋肉を使うと「できる」ようになる感覚はなんとなく伝わったようです。そんな共有を今後も体験させながら積み上げていきたいです。
●ウエイトトレーニング指導
その後、ウエイトルームでウエイトトレーニングの指導も行いました。フロアで行う自重トレーニングの中にもウエイトの動作は重複させ、いつでも練習ができるようにしたので、復習をしながら実践させてみました。トレーニングが初心者の子たちは素直に動きを真似てくれるところはあるので、意外とデッドリフトなども動きを理解してくれました。
少し負荷がかかった方が実際には取り組みやすいところもあります。すぐには適切なフォームで実施はできないかもしれませんが、少しづつ理解してくれたらいいなと思います。
●まとめ
高校1年生にトレーニングの指導を行いました。全体的に高校生のトレーニングはスポーツ動作の基本的な動き作りのドリルを多く取り入れています。適切に関節を動かせるようになれば、適切な筋肉が働くようになります。ストレッチング動作を見てもまだまだ修正が必要だし、指導が足りない(時間が足りない)ところはありますが、指導できる時には真剣に、丁寧に、繰り返し体づくりの大切さを教え、自分で取り組める環境を作っていきたいと思います。