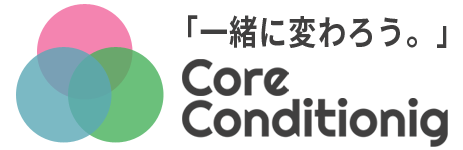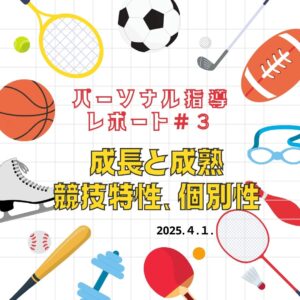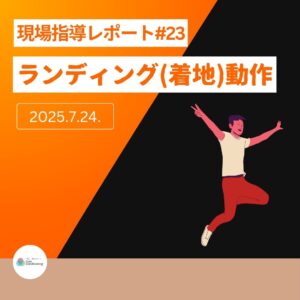アスリートから高齢者と幅広いクライアントと関わらせていただくと、人の人生における体の変化を、客観的に垣間見ることができます。若年層は弱く脆く、青年期はたくましく強く、そして壮年期は徐々に身体機能は落ちてゆくのだけれど、年齢を積み重ねやその人の生き方、考え方、ライフスタイルによって体力に差が出てくることを知りました。
今回は成長期の真っ只中、ジュニア期アスリートの指導をする際に気をつけているポイントについてです
<内容>
●パフォーマンスの土台となるStructural Stiffnessの獲得
●成長と成熟
●パフォーマンスの土台となるStructural Stiffnessの獲得
現在定期的に指導しているのは、アーチェリー競技の選手です。前回のコラムでも述べたように、TVで観たイメージと彼の言語感覚を頼りにしています。競技特性として、アーチェリーは対人競技ではないので(相手の動きに合わせて行動する競技ではなく、環境と自分の感覚で行う競技)、シンプルに「人間の体の構造上、弓を引くときに一番”安定する身体(Structural Stiffness)”を準備する」ことを基本とし、サポートを一番の目的としています。
Structural Stiffnessとは著書「ムーブメントスキルを高める」(2016,ブックハウスエイチディ発行)に書かれていた表現です。「安定性」という言葉”Stability”はよく使われますし、私もそう認識していましたが、この表現の方がイメージにピッタリなので使うことにしました。
簡単にいうと、建物の耐震構造であり免震構造のような、外力に対して崩れない、倒れない強さのこと。人間もこういう強さ、しなやかさが求められます。私が考えるアーチェリーのための体づくりはこの要素が一番「強い」んじゃないかと思っていて、そのためには上肢(腕)と肩甲帯、体幹部、そして股関節、下肢それらが全てバランスよく機能し、安定した姿勢で弓を引く、放つ動作のブレを少なくすることを目指しています。
●成長と成熟
「成長と成熟」の違いを示しておきます。「成長」とは体重や身長などの体組成など定量化できるものが変化することを示し、「成熟」とは子供時代から成人期への身体の変化の大きさの速度を示し*ます。この1年半で身長は伸び、体格も大きくなりました。これから筋量が増え、体重も増加しながら構造的な変化はまだまだ起こる印象です。
特徴的なことは体幹は非常に柔らかくしなやか、肩甲骨も可動性があるのに対し、ハムストリングスや下腿の後面の筋は柔軟性が欠如しています。それでも以前に比べるとストレッチングによって筋長が適応しているところをみると、身長はほぼ成長が完了したのかもしれません。同年齢の早熟型の選手を見ると、大筋群が発達している傾向があるのを経験しています。(その子の体と)比較すると、まだ完全ではないけれど成長は落ち着いてきている段階だろうという予測ができます。時期がくれば筋量が増えてくるのかな・・それも個体差はあると思います。予測は予測として、今の体で準備できることを提案するようにしています。
関節の可動域を確保することによって前述したStractural Stiffnessの準備(固有受容器という無意識で体のバランスや運動を制御してくれるセンサーが働く)が整います。そして関節が適切に機能するために使うべき筋・・下肢であれば中臀筋、上肢であれば前鋸筋、そして腸腰筋や体幹深部筋使うようなドリルを行っています。
「ハイパフォーマンスの科学」という本の第2章「若年アスリートの育成」冒頭には ”若年アスリートは成長と成熟により身体的、生理的、心理学的に大きな変化を経験している”そして”不適切なトレーニング指導や程度の低い教育学的アプローチをすると実際トレーニングに対する適応が減少したり場合によっては障害を招いたり快適な生活や健康を損なうことにもつながる”と書かれています。
現代の子どもは「外遊び」という貴重なコーディネーション能力獲得の機会、環境を奪われています。友達とどこまでもケンケンでスピードを競ったり鬼ごっこしたりする子は見かけなくなりました。雲梯にぶら下がったり鉄棒で遊んだりする環境は今は無いのだなと、小学校の鉄棒に紐が巻かれているのを見ます。体育の授業でもマット運動はやらないと聞きます。逆に、低年齢からの特定のスポーツ技術の習得は高くなっているように感じます。奪われたコーディネーション環境は別途「トレーニング」という形で提供することでケガ(外傷・障害)の予防を考えなければならないのですが、少し複雑な気持ちです。
●まとめ
成長期のアスリートをこうしてパーソナル指導できる機会はトレーナーとして非常に学びとなっています。実年齢と生物学的年齢は大きく異なること実感しながら、選手に合わせたドリル選択とプログレッションが可能なのがパーソナル指導の強みだと思います。ただ、新しい動作はうまくできなくて面白くないものです。一時的なパフォーマンス低下も起こることもある、ということを理解させるためにもトレーニングの目的を伝え、まず解剖学的、生理学的に正しい(教科書的な)ことから教えていくことも大事な時もあると思います。
このブログを書くにあたり、久しぶりに「ムーブメントスキル」の本を開きました。何度読んでも面白く、また学びになります。先人たちのトレーニングの考え方や深掘りの末に出てくる言葉の深さは本当にすごくて、興味深い。身体的な原理原則が必ず基盤になっているのでHow to(ドリル)ではなく、アイデアを与えてもらえます。ワクワクして勇気をもらえる一冊です。
*引用文献:High-Performance Training for Sports,David Joyce,Daniel Lewindon Editors,Human Kinetics,2014
*参考文献:ムーブメントスキルを高める,朝倉全紀監修,勝原竜太著者,有限会社ブックハウス・エイチディ,2016