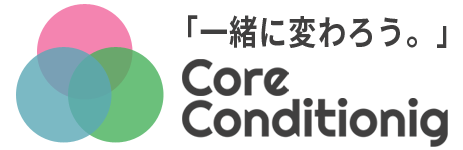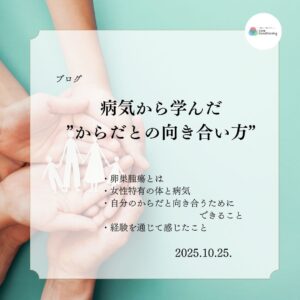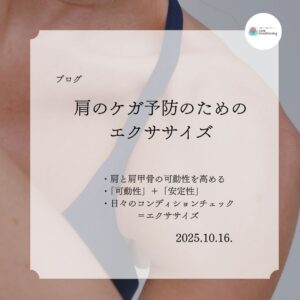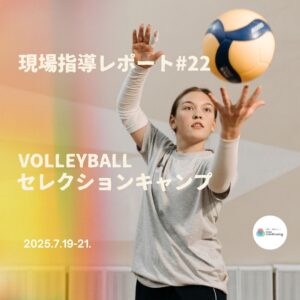研究1)によると日本の4年生大学男子バレーボールチームの1シーズンの傷害発生は、トレーニング時には腰部の慢性障害、そして試合時には足関節の急性外傷に留意が必要性があり、また2)高校生バレーボール選手では、男女ともに足関節、膝関節、脛部の外傷・障害が多いとの報告があります。
今回は、バレーボール競技に起こりやすいケガと身体要素、再発予防について考えてみたいと思います
内容
・競技特性による外傷・障害
・プレーで求められる身体要素
・ケガを予防または再発予防する
●競技特性による外傷・障害 リベロプレーヤーを除くポジション全てにおいて、跳躍(ジャンプ)を繰り返すなので、下肢のケガが多い傾向があると考えられます。
ジャンプ動作の反復による腱付着部の障害(脛骨過労性骨膜炎、ジャンパー膝、アキレス腱炎など)やジャンプ着地時に他プレーヤーの足部を踏み発生する足関節捻挫は、練習、試合に関わらず発生数が多いと認識しています。
ルール上「ボールをキャッチ(掴む)こと、床面に落とすこと」ができません。
相手プレーヤーの攻撃に対して瞬時にボールに対応するため、常にパワーポジションと呼ばれる”構えの姿勢”を持続しながら動き続けています。腰部への負担が大きいため、個々の体力を超えてしまうと、腰痛が発生し弱年齢(14歳〜17歳)では腰椎分離症という疲労骨折が多くみられます。
また頭上でボールをヒットするサーブやスパイク、ブロックが多いのも特徴です。打数が多くなると野球同様肩の障害(腱板損傷、インピンジメント)も発症します。
外傷ではフライングレシーブ時に肩が過伸展し、亜脱臼するケースも多く見受けます。10代に発症した肩の脱臼の再発率は90%と言われています。
このように「スポーツのケガ」は各競技の種目特性によってある程度は”予測可能”なので、競技中の動作を起こしているケガの因果関係を理解し、予防に努めることが重要と考えています。特に成長期の選手にはその時期特有のケガも多く、長い期間の安静や競技離脱は精神的にも苦痛を伴うため、できるだけ避けたいところです。
●プレーで求められる身体要素
ーディフェンス
ディフェンスにおけるプレーの主要なスキルとなるレシーブ動作には、腰の高さや両手を挙上し頭上でボールを扱う、いわゆる「ボールを相手にパス(渡す)する」動作や、床面に近い場所でのボール操作を求められる「ボールを拾う(掘る、という意味のディグ)」動作が多くみられます。
それぞれの姿勢はボールの受ける高さによって異なりますが、瞬時の股関節、膝関節、足関節の屈伸動作と体幹屈曲動作が必要で、なおかつボールをヒットしコントロールする身体操作能力はバレーボール競技の醍醐味であり、競技特有の技術です。
このようなプレーの発生には、股関節や足関節の可動域や体幹の多様な柔軟性と安定性が身体要素として必要だと考えています。
ーオフェンス
オフェンスにおけるプレーの主要なスキルとなるスパイク動作は空中に浮いたボールに場所、タイミングを合わせて自身も空中に浮き、狙った場所へヒットするというプレーです。
ジャンプ動作のメカニズムの観点から考えると、空中動作は地面に踏み込む瞬間の強さと方向と立ち上がりのスピードで決まっているので、技術力の高い選手はセッターの手からボールが離れる瞬間(セッターの動作を含め)に「ボールをヒットする場所」はある程度決定し、そこに向けてジャンプしているのではないかと考えています。
そういう観点から、ジャンプの踏み込みの姿勢、または踏み込む前の助走とその準備姿勢を観察し要因を見つけていきますが、ここでも股関節や足関節の可動域、体幹筋の強化は非常に重要です。それらに裏付けられた空中姿勢が、結果的に上肢への力の伝達と力強いボールヒットに繋がることを確認しています。
ー総合的な競技フィジカル
必要な体力要素は筋力、ジャンプ力(パワー)、敏捷性、スピード、柔軟性ですが、競技レベルに応じて高いスピードの中で持続的に運動するパワー持久力(無酸素性持久力)も必要かと思います。
高校生までは3セットマッチでトータルの試合時間は約1時間、1日に2~3試合設定なので、全身持久力の体力要素は”中程度”に位置付けられている競技です。
プレー時間で見ると、長くても20秒間プレーを約10秒間のインターバルで1セット(25点)50〜55回繰り返す体力がベースです。その20秒のプレー時間の中で数回のジャンプや短いダッシュ、上体の上下動、左右移動の動作が組み込まれています。
体力の向上の目的としてはこのような要素を繰り返すことができる体力トレーニングをプログラムすることが適当と考えますが、先にも述べたようにルール上「ボールを掴むことができない」ので技術が高く反復練習が求められ、習得に時間がかかることから相対的に練習時間が長い競技の1つも特徴かな、と感じています。
●ケガを予防または再発予防する 一度ケガから回復した選手が、再発するケースはよくみられます。例えば損傷した組織は修復期間が過ぎれば回復しますが、回復を待たずに練習再開した場合、組織の強度が戻らず炎症を繰り返しなかなか痛みが治らなかったり、他の部位に二次的な損傷が起きたりすることもあります。
残念ながら、強豪校と呼ばれるチームや能力の高い選手に多くみられる傾向があり、既往歴を聞くと、心が痛くなることも多く経験しています。
発症頻度の高い足関節捻挫は、軽視されがちな外傷です。重症度によっては1週間程度で復帰できる場合もありますが、受傷後よりも受傷翌日に腫れたり歩けなかったりする場合もあるし、成長期の子どもは骨折の可能性もあるので注意は必要です。足関節捻挫が十分に回復しなかったケースが後々にパフォーマンスに影響するのが足関節の可動域制限(背屈制限)、不安定性と足部機能の低下(扁平足障害など)です。適切な関節の動きが妨げられることで膝や腰に負担をかける動作が見られたり、靴の中で足部が必要以上に頑張っていたりすることがよく、見られます。
スポーツはケガがつきものですが、その判断はある程度の知識がないと難しいです。医療機関で診察をすることが一番ですが、もしも決断に迷う時には専門家に相談することも一つの方法です。
選手はプレーはできますが、コンディションやケガに関する知識は持ち合わせていないこと周囲の大人はよく理解し「誰のためのスポーツ活動なのか」子どもに変わって判断しなければならないこともあります。適切な行動を考え、選手の未来のためのリテラシーを持つことを願います。
●まとめ バレーボール競技特有のケガの発生頻度、プレー動作のメカニズムと最低限の解剖学や傷害の知識を持ち合わせた上で、私たちトレーナーはケガの予防というコンディショニング、再発予防というリコンディショニングに努めます。今後も少しづつ、ケガの予防に関する内容をお伝えできたらと思います。
何かこれらの情報が、皆さんの日頃のスポーツ活動に+αの発想につながるよう精進したいと思います。
参考文献
1)大学男子バレーボール選手における1シーズンのスポーツ損傷の疫学(資料),体力科学,第70巻,第2号165-173(2021)鈴木のぞみ,白幡恭子,石丸出穂,中村祐太郎,内野洋材,大沼正宏,櫻井雅浩
2)高校生バレーボール選手の急性外傷・慢性障害受傷傾向,日本バレーボール学会(研究発表),藤井壮浩ら,東海大学医科学研究所,2024