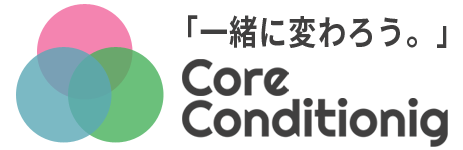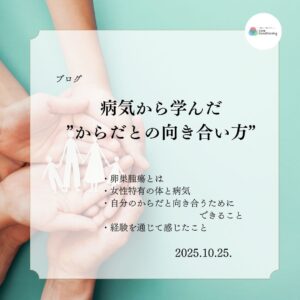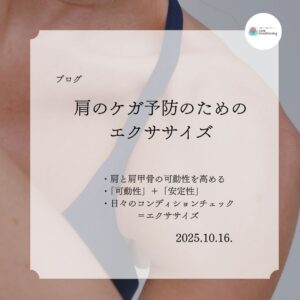4月12日に高校生男子バスケットボール部の大会サポートをしました。この日は打撲、筋痙攣、それと腰痛、あとは足関節捻挫の予防のテープの対応をしました
今回は試合間に先生方(監督、コーチ)や保護者と雑談する機会があり、このチームでの自分の仕事、トレーナーとしての役割を俯瞰する機会となりました。チーム関係者との関わりや役割、そして試合を通して感じたことについて記録したいと思います
<内容>
●先生(指導者)との情報共有①②
●保護者との雑談
●試合を通して感じたこと
●先生(指導者)との情報共有①
指導者の先生方からのコメントは選手と関わる上でとても重要な情報です。時に選手の不調の理由がはっきりしない、と聞くこともあります。
「明らかに選手のプレーがおかしい(普段通りの動きではない)から痛いのかと思い聞くと「大丈夫」という。本当に大丈夫なんだろうか・・?」
そういう話を聞いたあと、ハーフタイムのシュート練習で動作を確認すると、確かにシュートが入らないし走り方もおかしい。
本人と会話してみると、プレーは最近調子が悪い自覚はあるが、痛みなどはないとのこと。
「そうなんだね、でもやっぱり練習みてたら私もおかしいと思うし、先生が心配してるからちょっと確認してみようか・・」
選手と先生のコミュニケーションの”間”を埋めるような、そういう役割を担うことも大事な仕事の一つです。
●先生(指導者)との情報共有②
たまたま女子選手コンディションの話題となり、男子に比べてコンディションの波がある事を気にされていました。
高校生は女性ホルモン分泌が活発化するので、気分が不安定になってしまうことや過食になってしまう子もいます。こうしたホルモンの影響もあったりするようで、体重が増えてしまったと訴える子や、月経周期のタイミングによってはケガの一因になるとも言われています。
「実際にそういう生理現象がコンディション不良の原因だということに気づいていながら相談ができなかったり、そんな事すら考えられなかったりして自分を責めてしまうケースもあるんですよ」とお話しすると興味深く聞いてくださいました。
月経が及ぼすスポーツ活動への影響は、高校生の時分にはなかなか自分ごととして考えにくいし、指導者へこのような声が届くことも難しいと思います。また個人差があることなので、原因だと断定も出来ないし、婦人科への診察も受けにくい。
こうした専門的な情報と経験を持つトレーナーの役割、こういう場面でも感じました。
●保護者との雑談
私の経歴ついてのご質問がありました。我が子が(ケガをして)整骨院の先生や私のようなトレーナーと出会って、色々な体の変化を体感したこと(医療?)に興味があるようだと。
「(トレーナーと限定せず)私が選手に対応するような知識や技術はどこで学べるのだろうかと聞いてみたかったんです」とお声かけいただきました。私のことや考えも話をさせていただきながら
「人の体について何か興味があるのならば解剖学や生理学など人間の体の構造や機能の知識は(どんな方向へ進むにせよ)基礎だし、学校で専門知識を学んでおくのは一つの道だと思います」とお伝えしました。
必要なところへテープを貼ったり、動かしたりすると動きが変化する事を感覚的にも感じてくれていた事を親に伝えてくれていた事は嬉しかったです(役には立ててるようですね)。
●試合を終えての気づき
高校生をみていて、体づくりのためのトレーニングの大切さを感じました。
バスケットボールは、リバウンドからの爆発的なスタート(加速)によって攻撃のスピードが上がるし、ディフェンスも腰が落とせる(支えられる)脚力によって強力な”壁”となる。プレーのイメージや感覚的なものは理解できていても、そこに筋力だったりパワーだったりという体力要素が、選手が持つ技術の支えとなるため体力の有無は本当に大きいと感じてしまいます。
ある選手が、試合の終盤に私にこう言いました「試合の度に、同じようなケガを繰り返してしまう。(いつも教わるような)股関節のストレッチをすればそれは予防できるのか」と。最後の大会を前に「何かできないものか」と思ったのでしょう。
それはやってみないとわからないことだけど彼が自らその行動に出たら1ヶ月後は何か変化があるかもしれません。アイデアとしてはいいと思うと伝えました。
トレーナーは選手の”サポート”しかできません。長くこの仕事をしていると最終的に変わるのは選手自身、選手が自ら気づき行動を変えるまで待つしかないと思えるようになりました。
だからせめて今、求めてくれる選手や関われるチームに向けてトレーニングのサポートを頑張ろう、それしかできない立場だけど、できることはやりたいし伝えていきたいから現場で、選手に近いところで私は力を尽くしたいです。
彼は試合後、動画を撮らせて下さい、と私からトレーニングを習って帰りました。何かしら続けてくれる事を願います。そして全てのアスリートたちが、競技生活を全うする事を陰ながら応援したいと思います。