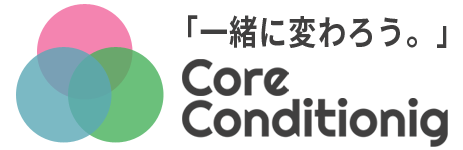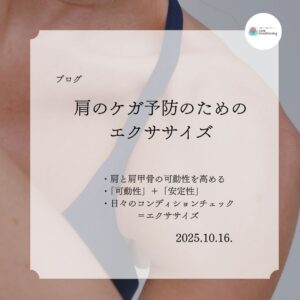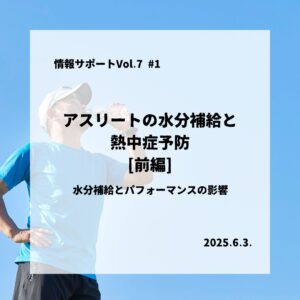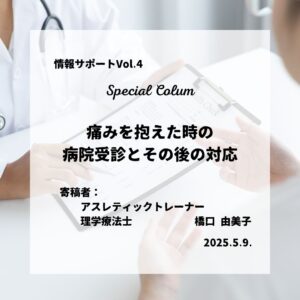第38回目「ケガ(外傷)が治る期間はどのくらい?」
突発的なケガをして病院で受診すると「〇週間または◯日安静に」「◯週間後にまた来てください」など言われることがあると思います。時間の経過とともに治ることはわかっていると思いますが、どういう理由で「安静期間」が示されるのでしょうか?
今回はケガ(急性外傷)をした時、どのくらいで治る(組織が修復する)のか、一般的な指標をまとめてみます。自分の「治ったかな?」の感覚と実際(治癒)とズレが生じる場合があるので参考にしてみてくださいね!
●ケガにおける組織修復の過程と期間
1.炎症期:受傷後 約1〜5日間
ケガをした直後から約3〜5日間の期間は、炎症反応(痛み、腫れ、熱感、赤みなど)が起こります。炎症反応は後に組織を修復するためには必要な現象であると言われています。出血、または内出血が起こった際は、損傷した血管に血小板が集まり、血栓(止血形成)が始まったり、白血球が壊れた細胞や異物除去を行います。
この期間の主な対処方法は①患部の安静②圧迫③(心臓よりも高い位置での)患部の挙上が基本です。痛みが強いようなら④冷却も効果的です
2.増殖期:受傷後3日〜3週間程度(靭帯などはやや遅れる)
炎症が落ち着くと、組織の修復が始まります。損傷部位を仮の組織で埋め合わせたり、新しい毛細血管が増殖し組織形成が活性化してきます。ケガの*重症度によっては軽い運動やリハビリもこのあたりから開始可能となりますが、まだ仮組織は脆いため、運動の強度が高いと再損傷しやすいので注意が必要です。
*重症度:ケガや病気の状態の重さを示す言葉。
3.再構築・成熟期:3週間〜数ヶ月(〜1年)
仮の修復材料も徐々に強固なものに置き換わる時期。骨折の場合は適度なストレスがかかることでリモデリング(仮骨が元の骨の構造と強度に戻っていく)が起こり、損傷した靭帯も強度や柔軟性が徐々に回復してきます。医師の診断の元、適切な負荷がかかる(=運動療法)ことによって、コラーゲン線維の配列が整い強度回復を促進させます。
逆に過剰な安静は治癒が遅れる原因にもなるので、専門医の指示を仰ぎ、しかるべきタイミング、方法でリハビリを行うことが結果的に早く、適切にケガを治すことができると言えるでしょう。
●ケガの種類による回復の目安
医師の診断による「重症度」によって固定・安静期間やリハビリ開始期間は異なります。
□ 打撲(軽度)
ボールや他選手の肘や膝などが筋肉・皮下組織に直撃し強い痛みを伴います。内出血があれば1〜2週間の安静、その後温熱療法やストレッチングに移行します
□ 筋肉損傷(肉離れ)
ダッシュやジャンプなどで瞬間的に筋肉が引き伸ばされる大腿部やふくらはぎで多いケガ。2〜8週間。部分断裂以上ではリハビリを経て競技復帰が必須となります(再受傷しやすいケガです)
□靭帯損傷(部分断裂)
足首や膝の捻挫などを指します。部分断裂の場合は6〜8週間。関節の動きが大きい部位なので、サポーターやテーピングなど一定期間の固定で患部の安静を図りつつ、段階的な運動療法が勧められます。
□ 靭帯完全断裂(手術例)
膝の前十字靭帯の断裂の場合は術後6〜12ヶ月と長期のリハビリ期間ののち、スポーツ復帰となります。
□骨挫傷
捻挫など適切にリハビリを行わないまま放置すると関節の不安定性が残り、骨や軟骨に影響が出る場合があります。長期的に痛みが続くこともあるので、医療機関で診察を受けましょう。骨などに影響があると2〜3ヶ月かかってしまいます。
●回復を早めるポイント
・炎症期は冷却+圧迫+安静が重要
・増殖期からは温熱療法・軽運動で血流を促進する
・再構築期にはリハビリ・ストレッチ・筋力トレーニングで適度なストレスをかけよう
・栄養でリカバリー:タンパク質・ビタミンC・亜鉛・鉄が組織修復をサポートします
スポーツでケガをすると「休みたくない」「不安」という気持ちになりますよね。でも、本当にその時に「無理ができる状態なのか?」「無理することが、最善の選択なのか?」は、然るべき診察を受け、専門家に相談することで選択肢や判断材料ができます。
アスリートは体が資本です。その時の感情や目の前の状況だけに囚われず、まずは現状を把握し、情報を集めたり相談しながら考えてみると、良い方向が見えてくるかもしれませんよ!
公式LINEアカウントお友達登録はこちら(毎月15日配信)