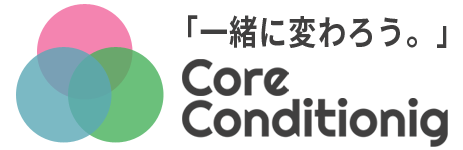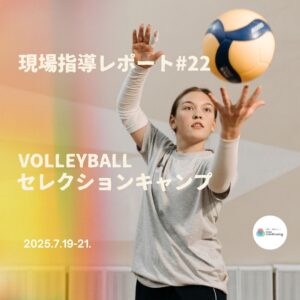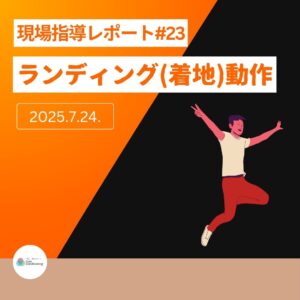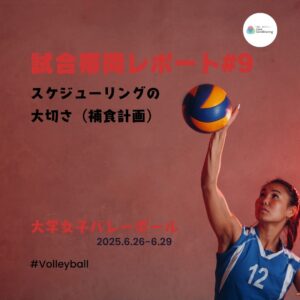7月19日〜21日の3日間、九州管内の大学女子バレーボール選手30名によるセレクションキャンプが行われました。
12月末に毎年行われる学連選抜対抗戦のメンバー選考と大学生の強化を目的に計画されたものですが、今年も選抜チームのトレーナーとして3日間、参加させていただきました。合宿間のトレーナーとしての関わりについて記録します。
<内容>
・体力測定の実施
・ウォームアップとリカバリー(ストレッチング)
・合宿通して感じたこと
●体力測定の実施 合宿のスタートは体力測定でした。測定内容は以下の通り①指高②ジャンプ計測(スパイクジャンプ・ブロックジャンプ)③両足3段跳び④9m3往復走⑤メディシンボール投げ(前投げ・後ろ投げ)⑥身長
今回の測定の目的はバレーボール指数*を算出したい、というものでした。主にジャンプの測定値と身長から算出されるもののようで、バレーボールの主要な体力要素を大人数で行う短期合宿では参考になるデータかもしれません。
単純に測定動作を観察するだけでも面白かったです。中でも一番興味深かったのは9m3往復走。9m間を3回切り返すスピードを計測するものでしたが、全体的に決して”効率が良い動き”とは言えず、身のこなし方が様々でした。おそらく、何度か練習すればコツを掴んで出来るのだと思います。この様子からジャンプ測定などと比べると、この動作は競技中に発生する頻度が低い動作であることが想像できます。もしかするとバレーボール選手の敏捷性能力を測定するには「Tドリル」のようなサイドステップや前後走が組み合わされたものや、「プロアジリティテスト」のように切り返しの距離に変化があるようなものの方が適切なのかもしれないと思いました。
またこのような体力測定を実施しているチームはほとんどないこともわかりました。事前アンケートで参加チームの体力トレーニング実施状況を調査しており、一番実施率が高いのがウエイトトレーニング(90%)、続いてジャンプトレーニング(74%)、自重トレーニング(50%)、ランニングトレーニング(40%)、アジリティトレーニング(30%)でしたが、せっかくトレーニングを実施しているのであれば選手の体力評価、実施状況の確認し、効果的なトレーニング計画を立案するためにも測定を実施することはおすすめしたいです。
*バレーボール指数とは:選手選考などの際に能力を客観的に評価するもの。算出方法:身長÷ネットの高さ×((ブロックジャンプ到達点-ネットの高さ)+(ランニングジャンプ到達点-ネットの高さ))
●ウォームアップとリカバリー(ストレッチング)これらが合宿中の主な担当です。与えられた時間(15〜30分)内で今回は状況に合わせて行いました。ここでも事前アンケートで「知りたい事、学びたいこと」の中で挙がっていた内容を取り上げながら進めていきました。初日はストレッチング、2日目以降はアジリティのコツを説明しながら段階的にスピードを高めたり、体幹トレーニングを取り入れてみたり、ジャンプ動作を解説したり…いろんな要素を取り入れながら、ポイントや目的を説明しながらウォームアップを行いました。
リカバリーとしてのストレッチングを練習終了後に行いました。”クールダウン”という行動の有用性や効果については未だ科学的な根拠に乏しいという認識ですが、基本的に柔軟性が乏しい選手に対して、基本のストレッチングの方法をゆっくりと学ぶ、丁寧に決まった行動(ストレッチング)をルーティンとして行うことで自身の体の状態を確認する、1日の練習を振り返る、などリセットの時間として10分程度行うものと捉え、指導しました。
●合宿通して感じたこと 率直に、普段対戦相手として戦っている選手同士が一緒に練習し、高めあうのはとてもいい刺激だと思いました。私も様々な選手の”動き”が観察できとても勉強になりました。身体について困っている事を相談に来てくれる選手もいて、初めて接する選手に、説明したり伝えたりする機会というのは自分のスキルを上げるチャンスにもなります。
「選考合宿」であり「強化合宿」という目的のもと、学生には”学びの場”を提供しながらウォームアップなどを実施しましたが、その先にいる若手指導者にも、コンディショニングの大切さを改めて感じてもらえたら、という思いもありました。途中で一緒に体幹トレーニングやストレッチングをする姿を目にしました。現実としてトレーナーに定期的に専門的な指導を受けられる環境づくりは簡単ではないことを知っているので、少しでも学生に学んで帰ってもらえたらという気持ちはとても大きかったです。
大学は自ら学び、自ら成長する場です。高校までの教育や環境の中でどれだけそういう考え方に触れる機会や考える機会を与えられたかというのも選手が大学で成長する要因の一つだと感じます。そう思うたびに「私には、何ができるのだろうか」と考えるのですが結局、何かを求めてくれる目の前の選手のために一生懸命向き合うしかできない。こういう機会を経験させてもらえたことに感謝して、日々の活動に引き続き励みたいと思います。