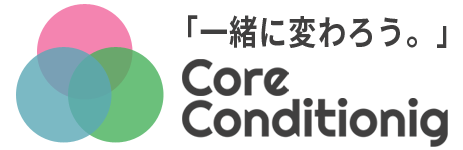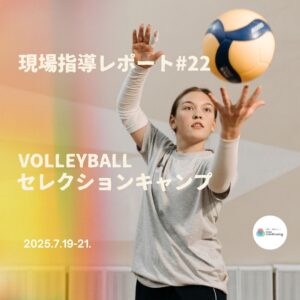九州大学春季リーグ戦が終了しました。最終順位は2位。4月末から約1ヶ月間、全8試合の大会でした。トレーナーとしてサポートの一部を記録します。
<内容>
・試合期間中の対応
・宿舎での対応
・試合を通して感じたこと
●試合期間中の対応
試合の移動や宿舎では選手と同じ行動をします。普段は関わる時間が少ないので宿舎や会場で体の状態をチェックしていきます。試合を観て、対応して、また次の日の試合を観て考える・・・の繰り返しです。最終リーグになると会場に到着してから試合までの3時間、昼食時間以外はひたすら選手の対応に追われました。
試合前の主な対応は「動きの最終チェック」がほとんどです。各自それぞれ体の準備はしていますが”もう少し動かす”手助けというのでしょうか(多分、その方がいいから来てくれているのだと思います)。この辺りは、普段からみていないとわからない(瞬時にマッチしない)ところなので、ここ(試合)に至るまでの準備状況が大事ですね。
試合前、試合間はベンチから選手の動きの様子を観察しています。試合までの”準備”がイメージ通りに動いているか、気になるところはないかパフォーマンスの中でチェックしていきます。セットを重ねるごとに動きが良くなる選手もいれば、ズレてくる選手もいるし、今回はコートサイドによって全く動きが変わる様子を見たので、そんな時私はどうすれば(どんな準備をすれば)いいのだろうか・・と常に私にも考えさせられます。
●宿舎での対応
宿舎に帰った瞬間からすぐ選手対応のスケジュールが送られてきますが、基本トレーニング指導です(そういう選手からの要望です)。ケアを要望する選手、必要な選手もいますが、基本、個々の課題に合わせて必要なこと(関節可動域を広げたり、体の使い方)を教えて次の日のアップやその後の各自の体づくりのヒントを与えるようにしています。
後半は1年生も初めて訪ねてくれました。痛みに関する相談でしたが「なぜこのような状態(痛み)が起こるのか(原因)」「どのように体を変えて行くのか(改善方法)」を学んでいくところから始めます。まずは自分の体を知ることが大事。このようなきっかけから日頃の練習前の体の準備が少しづつ形になっていくようです。
日を重ねると、徐々に体が動き出し、ドリルもステップアップしていきます。パンパンだった皮膚が緩んだり、痛みが緩和したり、いろんな変化を体感し重要性を伝えていける時間ができるのも大会に帯同する意味(仕事)です。これを日頃から継続して取り組んでくれたらいいのですが・・・
●試合を通して感じたこと
1週目の大会で試合を見た時、オフシーズン、そしてこれまでに私が関われる時間の中では、選手のプレーを十分みれていなかったことを痛感しました。選手個々の相談に応じたり、全体のトレーニング指導はブログでもご紹介してきたようにやっていたのですが、プレーから最終的にパフォーマンスに繋げていく理解まで、落とし込めていなかった。「ダメだな」と反省しました。
大会期間は学生たちといろいろ話をしました。普段考えていることを聞いたり、教えたり、相談に乗ったり、一緒に考えたりする時間は本当に大切です。中には期間中に大きく成長する選手もいました。以前とは話す内容も、行動も、大会を重ねるごとにプレーも変わる姿は嬉しく思います。丁寧に選手と接し、時間をかけた分だけ・・・ですが全ての選手に私1人では全ての対応は難しいので、当たり前に選手一人一人が考える力のレベルを上げていくためには何をすればいいのか、と学生トレーナーとも今後を話し合いました。
与えるばかりでは、本質的なことすら伝えられませんね、完全に指導不足。私の中で煮え切れない悔しさは、さらに考えて工夫していかなければならないと感じた今大会でした。