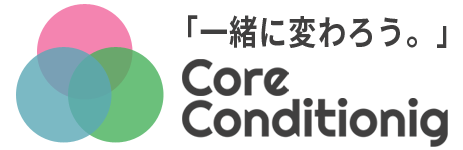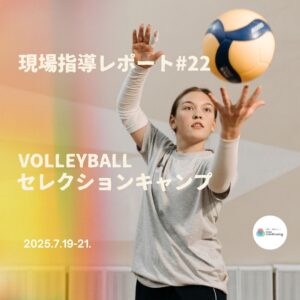高校総体の県予選、さまざまな競技が行われていますね。今週は高校生のバスケットボールの大会に3日間試合帯同しました。その様子の1部です
<内容>
・競技特性?
・動作の観察
・試合を通して感じたこと
●競技特性? 普段と違う競技を観ると、いろんな特性に気づきます。特に「構えの姿勢(パワーポジション)」は、動作特性からいうと違いはないはずなのに、明らかにバスケットボール選手の「構えの姿勢」の方が理にかなっている。スタートやシャッフル(横移動)、切り返し動作が速い。これはおそらく指導方法の影響が大きくて、バレーボール選手は「ボールを取る・コントロールする」という技術習得の前提があり「速く動く」<「低く構える」が最初は重要視されている気がします。バスケットボールも「低く構えなさい」「腰を落として」という指導を受けていると思います。でもバレーボールと違ってボールを保持でき、その状態でボールや相手の動きとかいろんな情報をキャッチする(見る)には、基本「上体を起こして」構えた方が良いし、その方が床反力を利用できるから機敏に動けます。
いずれにせよ、競技レベルが上がればバレーボールも「速く動く」能力が求められます。つまり「構えの姿勢」から修正が必要かもしれなくて、そういう要素をちょっと取り入れると、確実にシャッフルや切り返し、振り返りの初動スピードは上がるんじゃないかと思っています。もっと言えば、上体が起きると見える情報が増えるので、反応もしやすくなるはずですが、さて、長年積み重ねた姿勢をどうやって修正させましょうか・・・?
他にも、バレーボールは床に落ちそうな(低い)ボールも取りに行くので、バスケット選手より関節の可動域が必要なことも特性だと思います。逆にバスケットボール選手も、もう少し可動域を広げる努力をすればもう少し、膝を痛めたり足を攣ることも減るんじゃないかと思いました。
●動作の観察 バスケットボール競技の選手のサポートする際には「走る動作」と「シュート練習」を見て、だいたい特徴や調子の良し悪しを予測し、サポートの仮説を立てるようにしています。バレーボール競技よりも動きは見やすいです。例えば、今回は、試合終盤でポイントゲッターの選手のシュートが入らなくなった。軸のブレが見えたので、タイムアウト中にちょっと手を加えたら、その直後3ポイントシュートが入った(それが全てではないだろうけれど・・)。確実に姿勢のブレが修正できたことは確認できたし、こちらが意図して取った行動がこういう事象を招くこともあるし”その逆”(間違える事)もあります。でも1番”怖い”のはそれにすら気付けない事だから…今回のように最高の舞台で自信持って行動できるよう、日々トライ&エラーです。
●試合を通して感じたこと 男子チームの3年生は1年の頃から主力で、下学年の頃は体(フィジカル)が出来上がっておらず、大会期間中のコンディション不良に悩まされ、その都度サポートをする関わり方でした。3年生にとって最後の大会は私にとっても集大成。いい状態でコートに送り出せたし、それ以上に彼らの頑張りは素晴らしかった。
彼らが日頃どのように準備してきたのかはわかりませんが、引き出すことはできたという手応えは感じつつ、その上で思ったことはやはり「最後は体(フィジカル)が支えとなる」・・・それは誰しも十分わかっていることですが「どう準備していくか(日頃からトレーニングを計画していくか)」と日頃を振り返った時、今回も考えさせられる大会帯同でした。