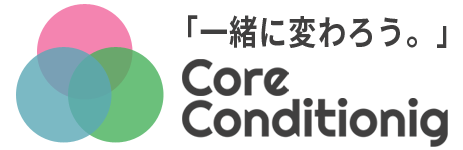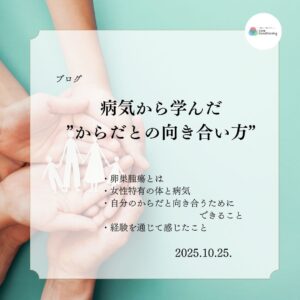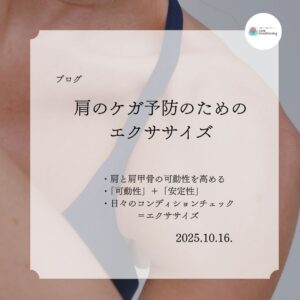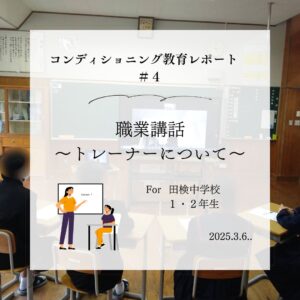体育大学にトレーナーとして関わらせていただくようになり、様々な学びを得る機会が増えました。先日は大学のメディカルチェック(体力チェックも含む)のお手伝で関わらせていただきました。自分のブース(関節弛緩性のチェック)をこなしながら、お手伝いの学生や普段はなかなか接点がない人とも雑談をするのもとても面白いです。
ちょっとした繋がりから、先日大学院でバイオメカニクスの研究と現場でトレーニング指導をしている学生さんとお話をする機会がありました。とても有意義な時間でしたので記録しておきたいと思います
<内容>
・大学院での研究
・競技特性の違い
・研究を現場に活かす
●大学院での研究
「情報サポート」のコラムで寄稿をお願いした、バレーボールのコーチングについて大学院で学んだ田中さん「大学院コーチとしての学びと着眼点」の中でも大学院について触れていましたが、自分の興味のある学問を専門的に深掘りしていく(研究する)ところです。今回話をした大学院2年生の岸さんは、バイオメカニクス(運動力学)の研究をしていて、専門種目はサッカー。主にプライオメトリックストレーニングの効果目的であるスプリント能力やジャンプ能力の改善のための研究をされてます。
自分で研究したことをどのように現場で選手に還元しているのかを尋ねてみました。
現在の研究内容の一部を聞かせてもらうと、プライオメトリックストレーニング指導の現場で使うキュー(指導言語、ここではインストラクション)によってジャンプ高に変化が出るという結果を踏まえ、コーチングにおいて選手にどのようにインストラクションしていくかということも焦点においているとのこと。トレーニング指導をバイオメカニクスの視点、さらにそれをどのような指導言語を使ってアプローチするかというのは、研究者であり指導者である、という強みだと思いました。
●競技特性の違い
コンディション管理についてもお互いの現状を共有しました。大学では全学生にONETAP SPORTS(株式会社ユーフォリア)が提供されているので、バレーボール部は毎日のコンディション状況やトレーニングによる負荷と主観的疲労度の入力を行なっています。サッカー部は独自のコンディション管理を行なっていると聞き、どのようなデータを集め、どのように活用しているのかを質問しました。
サッカー部は練習中の総走行距離と強度の高い(設定時速を超える)走行距離で個人にかかる練習強度と主観的な疲労度で算出しているそうです(GPSでデータを収集)。前日の運動強度や負荷でコンディションが可視化されているものを見せてもらいました。
では、バレーボールは?と考えた時、競技特性で一番体力が消耗される動作はジャンプ着地時にかかる身体負荷(ダメージ)です。研究*では「フルセットの試合の跳躍はセッターやリベロを除いて最大跳躍高の60%を超えていた」という報告があります。以前、バレー部でもVertというデバイスを使って、計測データを見ていましたが、その頃はまだ現場でコンディショニングに活かすところまで発展できませんでした。
選手のコンディションに合わせて走行距離を調節するといった練習のボリューム調整のようなコンディショニングは現段階でバレー部で活用できるような現実的なアイデアは思いつきませんが、簡易的に垂直跳びなどのジャンプ高のデータなどと日々のコンディションと合わせて予測し、監督、コーチへ提示できるようにしてみたいものです。
●研究を現場で活かす
私が学生の時「なぜ、これだけの施設があるのに私たち学生には研究されたものが還元されないのだろうか」と疑問に思っていました。今となっては「大学は研究機関だから」という単純明快なものですが、その学生の頃から興味を抱いていた「研究と現場」、こうして今、母校にトレーナーとして戻ってきました。
研究を現場で活かすメリットは、成功や失敗の”確率”を自分が実際に研究しなくても参考にできることだと思います。限りある練習時間の中で捻出する体力トレーニングの時間なので、少しでも効果的なトレーニング方法を考えたい。プログラムデザインのアイデアとして”確率”の高いもの押さえておく方がいいと思うし、研究を後ろ盾としておくとプログラムの仮説を立てやすいと感じます。
私はトレーナーなので、研究者のように何か一つのテーマを深掘りするのではなく目の前の選手に対応できる知識や情報を広く集めます。当然ながらSNSのような投稿者の知見で集められた情報よりも、論文をしっかり読んで自分が学び重ねた知識をもとに、リテラシーを高めてそれを現場に還元していく役割なのかな、と思っています。
いろんな「情報」や「アイデアの種」みたいなもの(ツール)が研究で、それらを常に引き出しに入れておきつつ、選手を観察する、関わる時間の中でひらめきのような感覚と瞬間に、そのツールを出して使う・・・現場ではそのような繰り返しを試しながらにはなりますが、トレーナーも一種の指導者なので、現場経験が大事!
「お互い、どうやって研究を現場に活かせるか、そして広く(フィジカルトレーニングの重要性を)どのように普及できるか考えていこう」
若い学生のアイデアや思考に学べきことは多く、私もまだまだ知らないことが沢山あるので、勉強していきたいと思います!
*引用資料:バレーボールの競技力向上のため慣性センサを用いたジャンプのコンディショニング管理に関する実践的研究,坂中美郷,沼田薫樹,和田智仁,前田明,濱田幸二(鹿屋体育大学),日本バレーボール学会第27回大会,2022,